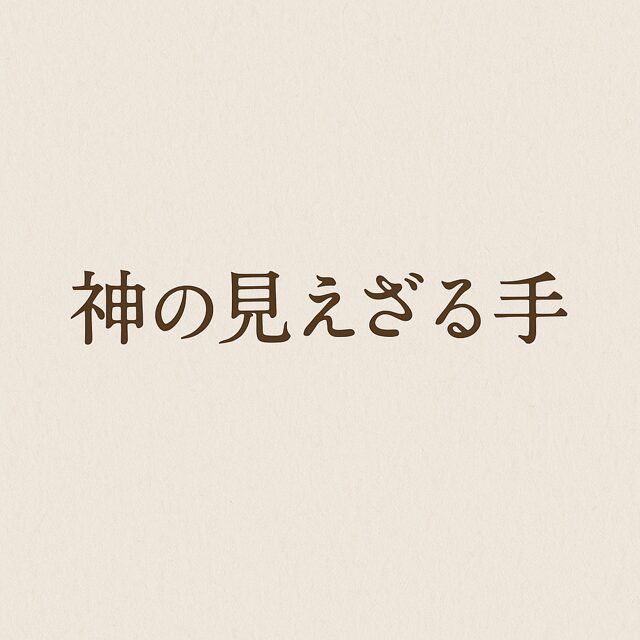
―哲学と旅館経営から紐解く、地域の未来づくり―
■ 自分のためが、いつのまにか誰かのために
「自分のために動いていたら、結果としてまわりの人々のためになっていた」
そんな不思議な経験はありませんか?
この現象を、18世紀の経済学者アダム・スミスは「神の見えざる手(Invisible Hand)」と呼びました。
彼はこう語ります——
**「人々が自己の利益を追求することで、結果的に社会全体の利益が促進される」**と。
これは単なる経済理論ではなく、現代の私たちの暮らしや仕事、そして持続可能な観光にも通じる、普遍的な真理です。
■ 旅館業に宿る「見えざる手」の力
私は長年、旅館という現場でこの「見えざる手」の力を何度も感じてきました。
たとえば、お客様に選ばれるために工夫を凝らして提供している「おもてなし」。
これは一見、自社の利益を追求する行為ですが、結果としてお客様の満足度を高め、良質な口コミが広がり、地域全体の観光レベルの向上へとつながっていくのです。
また、外国人観光客のニーズに応えようと取り入れた多言語対応やキャッシュレス化は、自館の魅力を高めるだけでなく、地域全体の受け入れ環境の整備を後押しする存在になります。
つまり、「自分のため」の努力が、知らぬ間に「地域のため」になっているということなのです。
■ 「見えざる手」に加えて「見えている想い」を
これからの時代、アダム・スミスが説いた「見えざる手」だけに頼るのではなく、
**意図的に、明確に、未来を思い描いて行動すること=“見えている想い”**がより一層重要になってきます。
・気候変動の中でも、四季折々の風景を守りたい
・後継者不足に悩む地域産業を支えたい
・誰ひとり取り残さない観光地をつくりたい
このような明確な意志を持ち、宿泊業や観光業に携わることこそが、サステナブルな地域づくりの原動力になるのではないでしょうか。
■ 哲学とSDGsの接点を見つめて
アダム・スミスの「神の見えざる手」は、単なる自由市場経済を正当化する言葉ではありません。
その背後には、「人間が他者や社会とどのように関わるべきか」という、深い倫理的問いが存在しています。
これはまさに、**SDGs(持続可能な開発目標)**が問いかけていることと重なります。
企業や個人の営みが、地球環境、地域社会、次世代にどのような影響を与えるのか?
この視点を常に持ち、自利と利他の調和を追い求める姿勢こそ、現代における哲学的実践であり、旅館業に携わる私たちの使命とも言えるでしょう。
■ まとめ:見えないつながりに気づき、見える未来を描く
「自分のためにやったことが、いつか誰かの力になっている」
そんな静かな連鎖が、地域を豊かにし、世界を少しずつ前に進めていきます。
これからの旅館業や観光業は、単なる“宿泊提供”ではなく、心の循環装置でもあります。
見えない力を信じながら、見える目標に向かって歩んでいく——
そんな哲学を胸に、私たちはこれからも、地域と世界をつなぐ小さな拠点であり続けたいのです。
📌 この記事で扱ったキー
