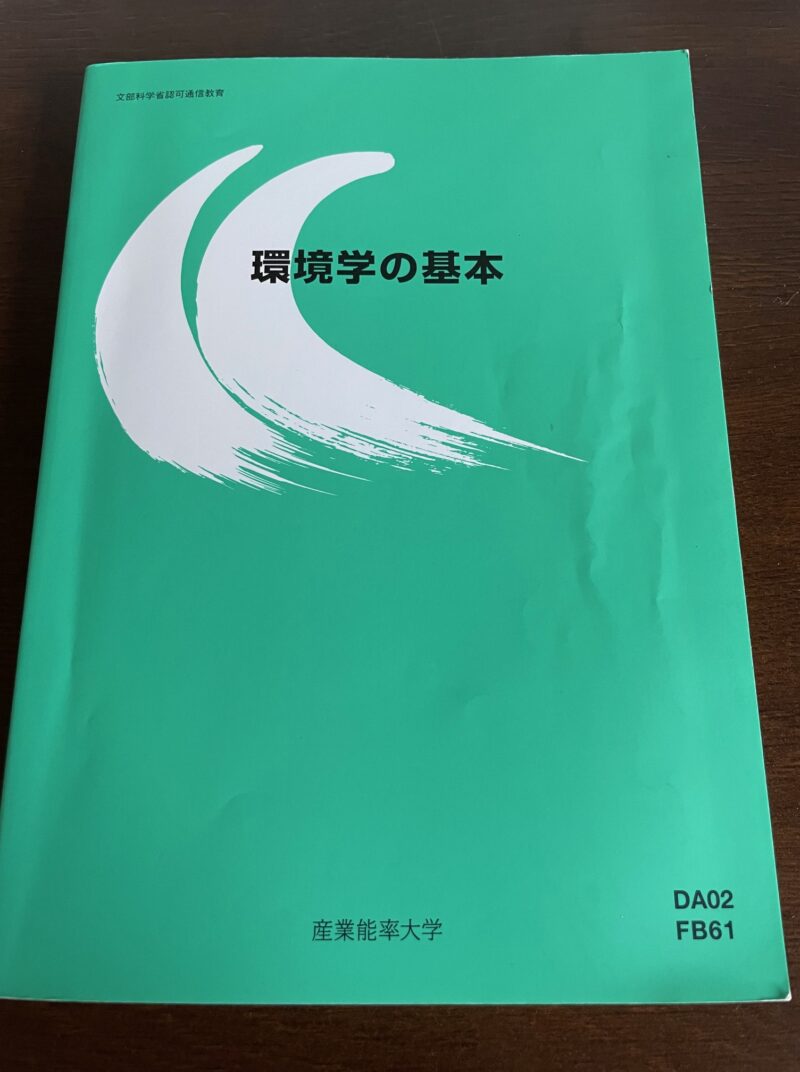
今回は、環境経営士としての第一歩を踏み出すきっかけとなった「環境学の基本」についてお話しします。
1. 環境学との出会い──産業能率大学での学び
私が環境というテーマに初めて関心を持ったのは、産業能率大学での「環境学」と「経営学」の履修がきっかけでした。実は、当初は環境問題にはほとんど関心がなく、「それは誰かが考えてやること」と他人事のように思っていたのです。
ところが、大学の会報に「環境経営士」という文字が偶然目に入りました。何気なく読んだそのページに「日本経営士会に問い合わせを」と記載されていたため、軽い気持ちでメールを送ったところ、必要書類と単位取得証明書を送ってくださいとの返信をいただきました。
その後、Zoomでの面接を経て、日本経営士会への入会とともに「環境経営士」の資格を推薦取得することができました。面接時に「どの分野に進みたいか?」と問われ、明確なビジョンを持っていなかった私は「食料の廃棄問題」と答えるのが精いっぱい。それでもその時の会話が、私の中で何かを変え始めたのです。
2. SDGsとの出会い──最初の一歩
「環境経営士」としての肩書きを手にしたものの、「では、何から始めよう?」と自問した私は、まずSDGs(持続可能な開発目標)を学ぶことに決めました。インターネットで調べていると、「サステナ経営検定4級[SDGsの基礎]」という資格を発見。すぐに受験し、無事合格しました。
4級に合格すると、「もっと深く学びたい」という意欲が湧き、そのまま3級にも挑戦して合格。その過程で、SDGsを実現するにはESG(環境・社会・ガバナンス)の観点も重要であることに気づき、「SDGs/ESGベーシック」の資格にも挑戦。ここでも新たな視野が広がりました。
3. サステナビリティへの深化──2級からの道のり
次なるステップは、「サステナ経営検定2級」でした。このレベルになると、企業経営と環境配慮の両立についての実務的な内容が多くなります。勉強の中で「カーボンニュートラル」や「Scope1〜3の排出量」の概念を深く理解するようになり、環境への視座が確実に広がっていきました。
2級の合格後、「サステナビリティオフィサー」の資格取得にも挑戦。これは環境省の認定制度と連動しており、合格と同時に「脱炭素アドバイザー」の資格も自動的に付与されます。現在、私はこの両方の資格を有しています。
4. 振り返りとこれから──大量消費世代の責任
バブル期の真っただ中に社会人となった私は、「大量消費こそが経済成長の証」と信じて生きてきました。しかし、それがもたらしたのは、大量生産・大量消費・大量廃棄という負のスパイラルです。
「作れば売れる」「捨てれば新しいものが手に入る」という考えは、もはや時代遅れ。これからは資源を守り、次世代に美しい地球を残すための経営視点が求められています。
私が環境学に出会い、環境経営士となり、さまざまなサステナ系資格を取得したのは、「次の世代のためにできること」を探す旅だったのだと思います。
5. まとめ──誰にでも始められる、環境学からの一歩
環境問題は、特別な人だけが取り組むものではありません。「興味がなかった私」でも、学びのきっかけひとつで、環境経営という道を歩き出すことができました。
今、この記事を読んでくださっているあなたも、ほんの小さなきっかけで新たな一歩を踏み出すかもしれません。環境学を学ぶことは、経営にも人生にも大きなヒントを与えてくれます。
