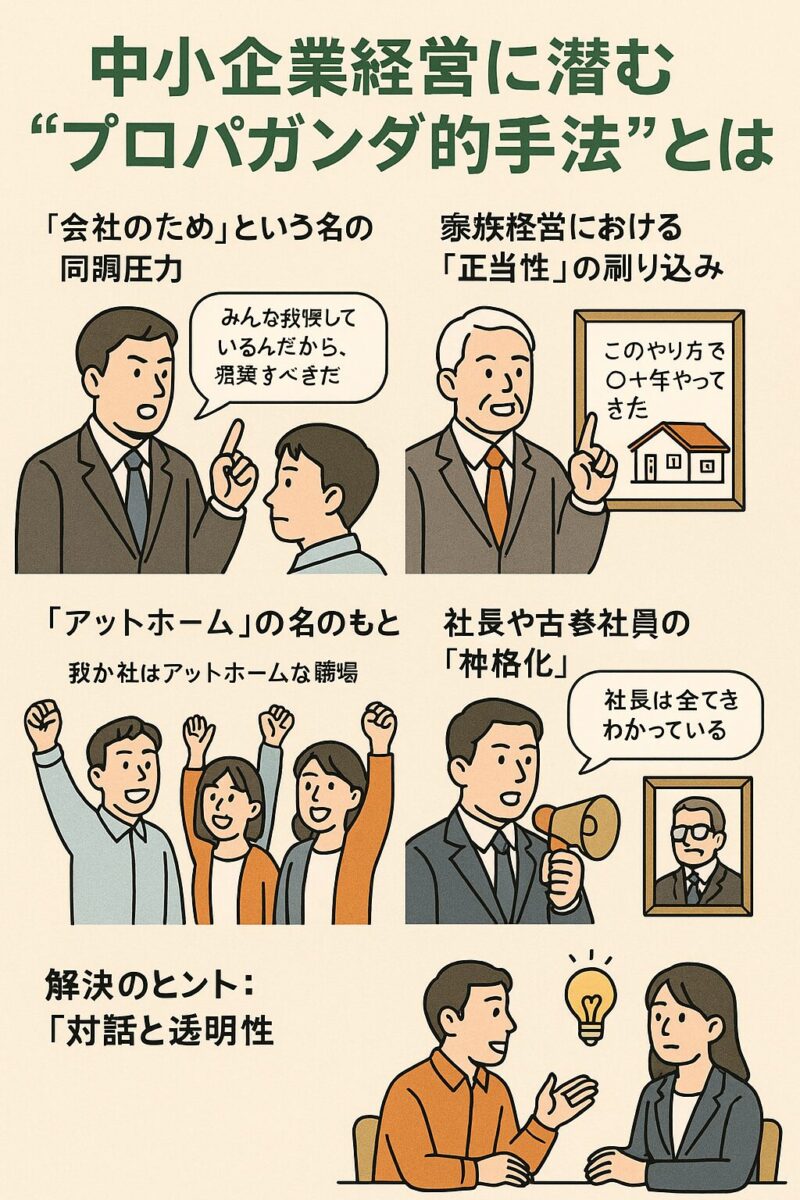
~対話と透明性が持続可能な職場をつくる~
中小企業、とくに家族経営の現場では、表立って問題視されることの少ない「プロパガンダ的手法」が組織運営に深く根を張っているケースがあります。これは国家規模の情報操作のような大げさなものではなく、職場の空気として染み込んでいる、一方的な価値観の押しつけや疑問を封じる同調圧力のことです。
このような“ミニ・プロパガンダ”は、持続可能な経営の障害となるばかりか、人材の流出や組織の硬直化を招くリスクがあります。本記事では、その具体例とリスク、そして脱却のためのヒントを探っていきます。
「会社のため」という名の同調圧力
「みんな我慢しているんだから、あなたも残業すべきだ」
「お客様第一だから、多少の犠牲は当然」
こうした言葉は、耳障りは良いものの、社員の声を封じる道具になっていないでしょうか。
中小企業では、トップの言葉がそのまま“社是”となるケースも少なくありません。疑問を持つことが悪とされる職場環境では、改善の芽も摘まれてしまいます。
家族経営における“正当性”の刷り込み
「このやり方で◯十年やってきた。だから変える必要はない」
「うちの家訓だ」「父の代からの方針だ」
こうした言葉も、変化を拒む無言の圧力として機能します。中小企業の多くは創業者の理念を大切にしていますが、それが時代遅れの常識や、感情的な忠誠心にすり替わっている場合があります。
このような風土では、新しい視点や正論であっても通らないことが多く、若手社員や外部出身者は無力感を覚え、やがて離れていきます。
「アットホーム」の名のもとに
「我が社はアットホームな職場です」「チームは家族だ」
一見すると温かみのある言葉ですが、これも一種の理想像の押しつけになっていませんか?
実態が伴っていないにもかかわらず、「家族のような関係」が前提になると、違和感や不満を表明しづらくなるという問題があります。
本来は、仕事上の関係と個人の距離感は適切に保たれるべきです。
社長や古参社員の“神格化”
「社長は全てをわかっている」
「昔は◯◯さんが寝ずに働いて会社を救った」
こうしたヒーロー像の持ち上げは、美談のようでいて、無理を美徳とする価値観を強化します。今の時代に合わない働き方を正当化し、「自分もそうあるべき」というプレッシャーにつながるのです。
プロパガンダ的経営のリスクとは?
| 項目 | リスク内容 |
|---|---|
| 意思決定 | 異論が出ず、誤った方向でも止められない |
| 人材定着 | 理不尽さを感じた若手が早期離職する |
| 組織文化 | 多様性が失われ、柔軟な発想が生まれにくくなる |
| 外部評価 | 時代遅れの印象を与え、採用や取引に悪影響 |
特に人材不足が深刻な中小企業では、「辞めたくなる雰囲気」があるだけで致命的になりかねません。
解決のヒント:「対話と透明性」
1. フィードバックの場を設ける
若手や現場の声を吸い上げるために、意見交換の場や匿名アンケートの導入が有効です。
提案に対してリアクションがあるだけで、社員の心理的安全性は大きく向上します。
2. 経営情報をオープンにする
会社の方針、売上目標、人事の方針など、**できるだけ「見える化」**することが信頼を生みます。
不安の正体は「わからないこと」。情報開示は、社員の納得感と安心感につながります。
3. 正論より“共感”の伝え方を
経営者や上司が何かを伝える際、ロジックだけではなく感情にも寄り添う表現が大切です。
「あなたの立場なら、私もそう感じるかもしれない」という共感を示すことで、信頼関係が築かれます。
サステナブル経営の第一歩は“対話”
サステナブル経営とは、環境配慮だけでなく、人の持続性をどう確保するかでもあります。
社員の声を聞き、透明な経営を行うことは、離職を防ぎ、会社を次世代につなぐ礎となります。
支配人が日々ご体感されている「一族経営の限界」や「現場の沈黙」も、こうした“ミニ・プロパガンダ”の構造が根底にあるのかもしれません。
今こそ、沈黙ではなく対話を。閉鎖ではなく開示を。
それが、持続可能な未来を築く第一歩です。
