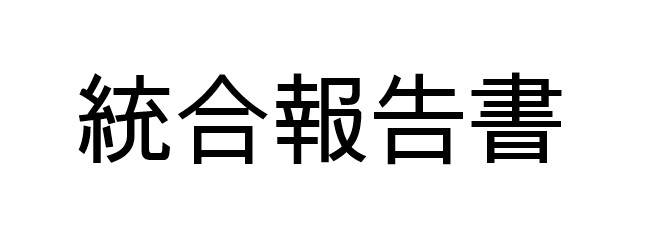
中小企業においても、近い将来「統合報告書」の作成が求められる時代がやってきます。
これまで大企業や上場企業が中心だった統合報告書。しかし、サステナビリティ経営や人的資本開示の重要性が増す中で、中小企業にもその波が確実に押し寄せています。先んじて備えることで、企業価値の向上や信頼獲得につながるのです。
統合報告書が中小企業にも必要とされる背景
① サステナビリティ経営の普及
気候変動、地域社会との共生、従業員のウェルビーイングなど、企業に求められる社会的責任は年々拡大しています。中小企業も例外ではなく、「環境・社会・ガバナンス(ESG)」を意識した経営が、今や競争力の源泉となっています。
② 非財務情報の開示圧力
経済産業省や金融庁が主導する「人的資本可視化指針」や「サステナ情報の開示ガイドライン」などの整備により、企業は財務データだけでなく、人材・環境・地域貢献などの「非財務情報」の開示が求められつつあります。
③ サプライチェーン全体への要求
大企業がサステナ経営を実施する中で、そのサプライチェーンに属する中小企業にも、同様の取り組みを要求する傾向が高まっています。統合報告書は、その対応能力や姿勢を可視化する手段となります。
実際に統合報告書を導入した中小企業の事例
① 製造業A社(従業員80名)
地域密着型の部品製造業であるA社は、取引先の大手自動車メーカーから「人的資本情報の報告」を求められました。そこで、2023年に簡易版の統合報告書を作成し、自社の人材育成・SDGsの取り組み・地域活動をレポート形式でまとめました。
結果、取引の継続にとどまらず、新規案件の獲得にもつながり、営業ツールとしても活用できることを実感。社員のモチベーション向上にもつながりました。
② サービス業B社(従業員45名)
地方都市で複数の飲食店舗を経営するB社は、「サステナ経営」を宣言し、自治体や地元金融機関と連携して統合報告書を発行。再生可能エネルギーの導入や地元食材の活用、人権ポリシーの明文化などを一冊にまとめた報告書は、地元メディアでも取り上げられ、採用活動に大きな効果がありました。
統合報告書は、今後の中小企業経営において「必須」となる可能性が高いです。
義務ではない今だからこそ、「自発的な開示」は企業価値を高めるチャンス。ステークホルダーに信頼され、持続可能な経営を目指すうえで、統合報告書は最適なツールです。
統合報告書と聞くと、「難しそう」「コストがかかる」といったイメージがあるかもしれません。しかし、最初は3〜5ページの簡易版からのスタートでも十分です。以下のような構成であれば、取り組みやすく、発信にも活用できます。
統合報告書の簡易構成例(5ページ構成)
- 会社概要と経営理念
- 財務情報(売上・利益推移など)
- 非財務情報(人材育成、環境対応、地域連携など)
- 今後の方針と目標(SDGs・脱炭素・DXなど)
- 社長メッセージ・価値創造ストーリー
PDF化してホームページに掲載するだけでも、「見える化」したサステナ経営の証となります。
- 中小企業 統合報告書
- サステナ経営
- ESG開示 中小企業
- 非財務情報 開示
- 持続可能な中小企業
- 統合報告書 作成 方法
- サプライチェーン ESG対応
統合報告書の作成は、中小企業にとって**「信頼と共感を得るための時代対応型ツール」**です。社会課題への意識が高まるなか、顧客・金融機関・取引先から選ばれる企業となるためにも、まずは簡単な一歩から始めてみませんか?
今こそ、「小さな企業から、確かな信頼を発信する」時代です。
